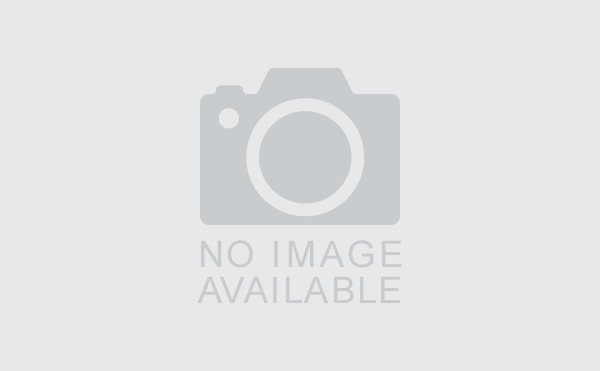飲食店の社長が学ぶ,労災事故増加の理由
社長が学ぶ飲食店の労災事故増加の理由
みなさん、こんにちは。
日本の労災事故は長期的には減少傾向にあります。
ただ飲食店を取り上げてみると、労災事故は現在も増加しています。
飲食店だけ増加している理由、あなたは、なぜだと思いますか?
飲食店には、ファストフード、ファミリーレストラン、居酒屋、配達飲食サービスなど様々な業態があります。
労災事故防止を推進するためには、それら業態の特性を踏まえる必要があります。
今回は、あなたと飲食店の代表的な業態それぞれについて、労災事故の特徴、安全教育のポイント、企業の安全活助事例をまじえて、一緒に考えていきましょう。

飲食業の労災事故を社長と学ぶ
社長が考える飲食店の労働事故を防止する方法
休業4日以上死傷労災(以下、死傷労災)の推移をみると、平成17年から平成27年の間、製造業はー28.1%、建設業はー31.9%と大幅に滅少しました。
逆に、飲食店は+21.6%と大幅に増加しています。
ずばり!これには明確な理由があります。

飲食業の労災事故を社長と学ぶ2
飲食店で「働く人のための安全」の意識は?
飲食店の実態調査を行ってきましたが、事業場の多くは「お客さまのための安全」はあっても「働く人のための安全」はあまり見受けられませんでした。
飲食店はの労災事故の大幅増加の理由です。
厚生労働省「第12次労働災害防止計画」に掲げられたとおり、まず、大規模店舗・多店舗展開(チェーン展開)企業などを重点とした労働災害防止意識の浸透・向上が求められます。
飲食店には様々な業態があります。
業態特性を踏まえた労災事故防止対策が必要です。

飲食業の労災事故を社長と学ぶ3
例えば、飲食店の労災事故の一つに包丁による切れ・こすれ災害があります。
ハンバーガーショップではほとんど包丁を使わず切れ・こすれ災害はあまり発生していません。
一方、カフェでは切れ・こすれ災害は多いものの、それは包丁ではなく、割れたグラス等によるものです。
このように、労災事故は業態特性によって違ってきます。
飲食店の労災事故は転倒災害が、最も多い
平成24 ・ 25 年、飲食店の死傷災害を事故の型別にみると、「転倒」(27.7%)が最も多い。
次いで、「切れ・こすれ」(25.4%)、「高温・低温物との接触」。「高温・低温物との接触」(14.6%)、「動作の反動・無理な動作」 (7.1%)の順に多く発生しています。
業態別にみると、ハンバーガーショップは高温・低温物との接触災害(ヤケド)が最も多い。
回転寿司は切れ・こすれ労災が転倒労災を大きく上回っています。
また、配達飲食サービスは交通事故(道路)が最も多発しています。

飲食業の労災事故を社長と学ぶ4
飲食店、労災事故の課題
あなたと飲食店の労災事故増加の理由を考えてきました。
いかがでしたか?
また一緒に勉強していきましょう。